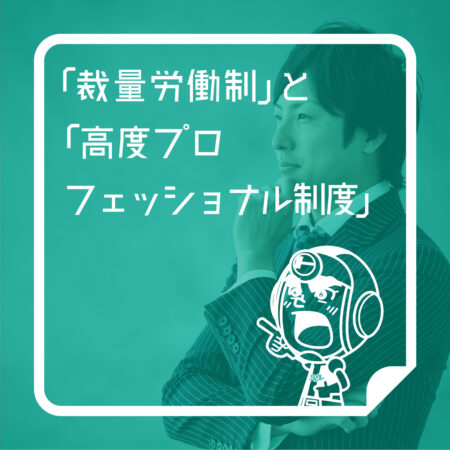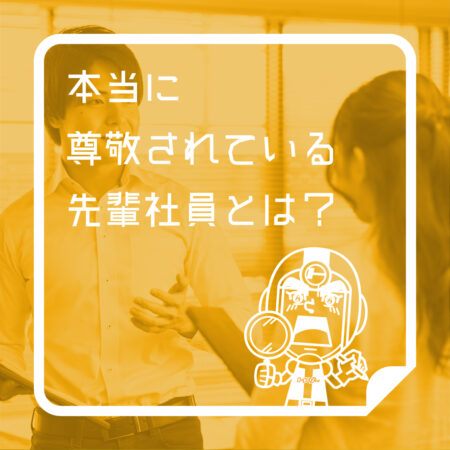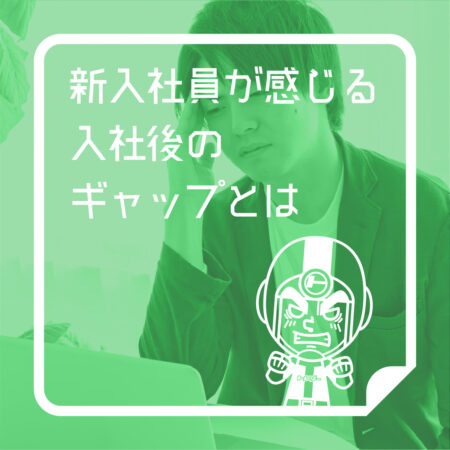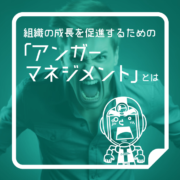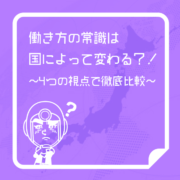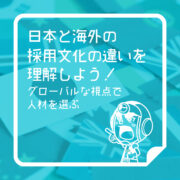溜め込む前に対策を!社員のストレスチェック

公開:2017年11月14日
更新:2019年07月29日
会社に対する「ストレス」が原因で、離職に至るケースも多々。
社員のストレス管理は、離職防止にも有効です。
そこで今回は、社員の離職対策の1つである『ストレスチェック』についてご紹介していきます!
社員のストレス状況を把握し、フォローを実施することと合わせて、ストレスの原因を解消することが離職の対策になります◎
目次
約6割が仕事に対して『ストレス』を実感
なんと、仕事や職業生活に強い不安・悩み・ストレスを感じている労働者は、全体の58.3%にのぼります。
約6割がストレスを感じながら働いている状態。
※厚生労働省が平成29年に発表した労働者健康状況調査結果による
重度のストレスを抱えた状況が続くと、それが原因で離職に至るケースも。
1度強いストレスを感じた場合、それを払拭するのは困難なため、事前の対策が重要になります。
そこで、社員のストレスを予防する方法として有効な『社員のストレスチェック』について、詳しくご説明していきます!
『ストレスチェック』とは
ストレスチェックとは、『ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる』というものです。
簡単にいうと、自分のストレスがどの程度あるのかを把握すること。
より働きやすい職場環境をつくるため、企業には『ストレスチェック』が義務付けられています。
※労働者が50名以上の企業が対象
- 頻度:年1回以上
- 対象者:契約期間が一年以上、または通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上の労働者
仕事によるストレスが原因でメンタル不調を訴える労働者が、年々増加傾向にあったため、その対策として政府が労働安全衛生法の一部を改定し設けました。
では、「ストレスチェック制度」により、「高ストレス」であると判断された従業員がいた場合、どうすればよいのでしょうか。
ストレスチェックの判断基準
まず、高ストレス者と判断する基準は、大きく分けて2つあります。
- 1つ目:事業所の中でおこなう衛生委員会で、産業医の意見をもとに判定基準を設ける方法
- 2つ目:厚労省が決めた点数によって、高ストレス者を判断する方法
一般的に厚労省では、チェックの結果上位10%の方を高ストレス者として定めています。
しかし、業種・職種によって異なる可能性があるため、一度厚労省の基準で実施し、その傾向をもとに独自で基準を作っていく方法がオススメ。
社内の従業員の中に高ストレス者がいた場合、対応のフロー例は以下のようになります。
・健康状態確認セルフチェック票への記入(高ストレス者)
・情報提供書(企業から産業医)
・ストレスチェック後の面接指導結果報告書(産業医記入)
・ストレスチェック後の面談指導事後措置に掛かる意見書(産業医記入)
ストレスチェックの結果が届いた後、高ストレス者が面談を希望するかどうかは本人の自由です。
強要できないところが少し難しいポイントですが、実施者や産業医などが本人に働きかけることはできるため、面談を行うよう促すことが大切となってきます。
高ストレス者は、うつ病などの精神的な病気になるリスクが極めて高く、ストレスチェックや面談が形骸化しては意味が薄れてしまいます。
カタチだけになってしまわないよう、しっかりと従業員のストレス状況を把握し、改善に努めましょう。
また、高ストレス者へのフォローだけでなく、ストレスの原因を追求し根本的な解決に図ることが、離職防止には効果的です。
目的の共有とアフターフォローで効果UP
一人採用するにも苦労する時代。
社員の離職はできれば避けたいですよね。
そこで重要になってくるのが、『日々の心のケア』。
つまり、メンタルヘルス不調となる前の対策です。
平成27年12月にストレスチェックが始まり4年が経ちました。
「ストレスチェック制度」を実施するも、正直イマイチ・・・という企業さんも多いのではないでしょうか。
その要因の1つに従業員のストレスチェックへの「理解不足」があると思います。
ストレスチェックに対して、「何のためにやっているの?」「情報が知られるのが嫌だ」「適当に書こう」等という意見が多いのが実態。
このようなネガティブなイメージが横行しないためにも、ストレスチェックを実施する以上は、その後のフォローは必須です。
きちんと目的などを共有し、結果に対する行動で意味のある「ストレスチェック」を実施しましょう。
日々の工夫でストレスをためない!
また、ストレスは日々の中でも簡単に軽減することができます。
- ストレスを吐き出す
- デスク(PC)から離れること
ストレスの対策として一番効果的なのは、ストレスを口から発することであり、グループディスカッションやマネージャーとの1対1での状況確認をすることで、ストレスを共有することができます。
そして、どの社員に対してもはけ口ができる場を与え、解消法についてアドバイスすることが大切です。
また、デスク(PC)から離れることも効果的。
例えば自転車で通勤するとか、ヨガを習うとか、週に1度はウォーキングするとか、なんでも良いのです。
アクティブな体が健全な精神を作るということが、研究で分かっています。
毎日の小さな工夫で、ストレスを溜めないようにすることが、実は1番の予防策かもしれませんね。
【まとめ】
今回のブログをまとめました。
- 6割近い労働者が、仕事に対してストレスを実感
- ストレスが原因で離職する人も多数
- 『ストレスチェック』は目的の共有と実施後のフォローが必要
- 離職防止は、日々の小さな工夫の積み重ね
ストレスチェック制度に対して、あまり効果を感じられていない方は、是非参考にしてください!
また、日常生活の中で少しずつストレスを発散させてあげることも大切です。
病気になることは、従業員も企業側も幸せなことなどありません。
そのため、ストレスチェックや面談が形だけのものにならないように、ストレスチェックのイメージを改善することから始めると、良い解決の糸口となることが期待できます。
ストレスのためない職場環境をつくることで、離職防止しいては人材定着に繋がります◎
人材採用には社員の口コミによる影響も強いので、人がやめない職場つくりを一緒に目指していきましょう!
また、採用戦略研究所では人材定着のお手伝いツールとして『ミルベイ』をご提供しております。
詳細はお問い合わせくださいね!
合わせて読みたいブログ
▷小規模企業の人手不足
▷内定辞退の面接で防ぐ!求職者が望む面接とは?
▷19年卒の入社式~退職代行サービスの利用が拡大~
お問い合わせ先
株式会社採用戦略研究所 ブログ担当者
大阪府大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル 9F
TEL:06-4300-7120 MAIL:share@rs-lab.jp![]()
![]() @saiyousenryaku 🔍
@saiyousenryaku 🔍
 ライター 高田ゆかり
ライター 高田ゆかり2018年8月から採用戦略研究所でインターンシップを経験。
その後 2019年4月に新卒入社しました!
現在は、在宅でブログや原稿を作成したり、画像もつくっています。