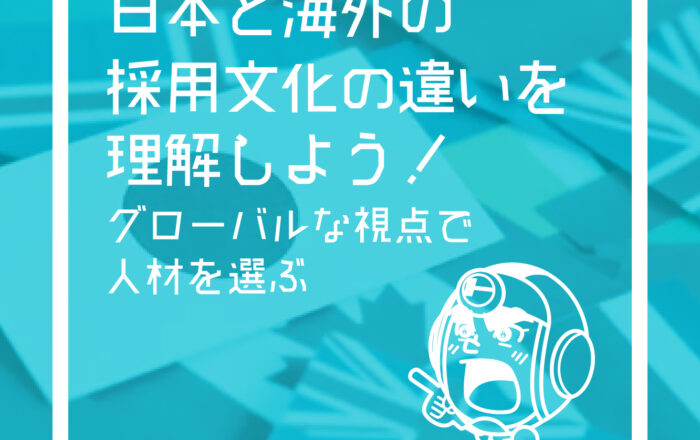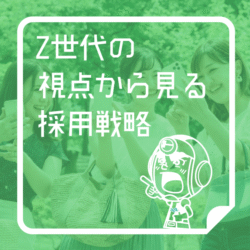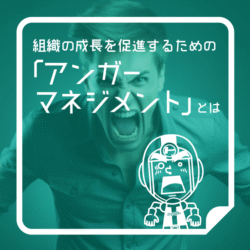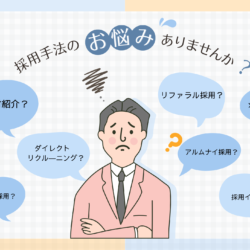~グローバルな視点で人材を選ぶ~
公開:2025年3月22日
更新:2025年3月22日
近年、企業の採用活動はますますグローバル化が進み、国ごとに異なる文化や慣習が採用戦略に大きく影響しています。
日本国内だけでなく海外の採用方法を理解し、国際的な視点を持つことは企業にとってますます重要になっています。
そこで本ブログでは海外と日本の採用の特徴を比較し、それぞれの強みや課題、企業が今後採用活動を強化するためのポイントをまとめました。
第1章 日本と海外における採用プロセスの違い

採用プロセスは企業にとって最も重要な業務の一つですが日本と海外ではそのアプローチに大きな違いがあります。
採用文化や戦略は企業の規模や業界にも影響を受けますが文化的背景や働き方の違いが採用プロセスにも強く影響を与えています。
そこで最近の実情を踏まえ、日本と海外の採用プロセスの具体的な違いを見ていきましょう!
<日本の採用プロセス〉
日本では採用活動がとても形式的であり、企業の文化に合った人材を「長期的に育てる」ことが重視される傾向にあります。特に大企業では学生を対象とした一斉採用(新卒採用)が中心であり、以下の特徴が見られます。
新卒採用の重視
日本企業の多くは新卒採用を中心に組織を構築しています。新卒一括採用は学生が大学を卒業するタイミングで一斉に行われ、求められるスキルは主に「潜在能力」や「企業文化に適応できるか」に重きが置かれる傾向があります。専門知識やスキルよりも将来性や組織との相性を重視するため、特定の職種におけるスキルよりも「成長の余地」に期待がかけられるのことが多いことが特徴と言えます。
採用面接の形式
面接の数が多く、また形式も非常に堅苦しいことが多いです。企業ごとに異なりますが、一般的には【書類選考→一次面接→二次面接→最終面接】という流れがあり、最終面接においては役員が参加することもあります。また面接は集団面接やグループディスカッションを取り入れる企業もあり、協調性や集団での働き方を評価する傾向があります。
終身雇用の文化
日本の企業では採用した人材を長期間育てることを前提としている企業が多いです。新卒入社後は職種や部署が変更されることが一般的であり、社員は長期的なキャリアパスを意識して働きます。このため採用プロセスでは「自社で長期間働き続けられるか」という点が重要視されます。
採用活動の時期
日本の企業は通常、1年に1回の「採用活動シーズン」を設けています。多くの企業がこのシーズンに集中して採用活動を行い、学生や求職者に対して同時に複数の選考を行うのが一般的です。そのため企業側も候補者を評価する時間に制限があり、より形式化された選考プロセスになります。
<海外の採用プロセス〉
一方で海外、特にアメリカやヨーロッパの採用プロセスは日本と異なるアプローチをとっています。特に近年ではリモートワークや柔軟な働き方が主流となり、多様な採用方法が生まれています。
以下、具体的な特徴を見ていきましょう!
経験とスキル重視
海外の採用では経験やスキルが非常に重要視されます。特に中途採用においては過去の業務経験や実績が評価されることが一般的です。応募者は「何ができるか」「過去にどんな実績を上げたか」を証明しなければならず、書類選考や面接では実務的なスキルや業務への適応能力が求められます。
採用プロセスのスピード
海外では採用プロセスが比較的迅速です。特にテクノロジー企業やスタートアップ企業では採用決定までの時間が短縮される傾向にあります。多くの企業では最初の面接から内定まで1〜2週間で決定することもあり、即戦力を求める傾向が強く見られます。このため応募者側もスピーディに選考を進め、仕事に適応できるかを早期に評価されることになります。
多様性とインクルージョンの重視
近年、特に欧米の企業では多様性やインクルージョンの観点から採用においても平等な機会を提供することが求められています。性別・年齢・人種・国籍に関わらず、様々なバックグラウンドを持つ人々を採用することが企業の戦略として重要視されています。このため面接では「適切なフィット感」よりも「多様性のあるチームづくり」が重視される傾向があります。
面接の形式
海外では面接形式が比較的フレキシブルと言えます。電話面接やビデオ通話面接が一般的であり、リモート採用活動が多く行われています。また企業によってはオンラインプラットフォームを通じて自分のスキルを証明するテスト(例:コーディングテストやセールスピッチ)を取り入れていることもあります。このように遠隔でのやり取りを積極的に活用する企業が増加しています。
インターンシップとパートタイム採用
海外ではインターンシップやパートタイム採用が採用プロセスの一環として広く利用されています。特にアメリカではインターンシップを通じて候補者と企業が相互に評価し合うシステムが確立されており、その後のフルタイム採用につながるケースが多いです。企業は候補者の能力や適応力をインターンシップ期間中に見極めることができるため、長期的な採用活動よりも柔軟な評価が可能になります。
![]()
日本と海外の採用プロセスを比較すると採用の目的や求められるスキル、選考方法に明確な違いがあることがわかります。
このような違いは各国の企業文化や経済状況、さらには労働市場の特性によって影響を受けています。
日本は「育成型」の採用を中心に安定的な成長を目指す企業が多いのに対し、海外では特にテクノロジー分野やスタートアップにおいて「即戦力」を重視する傾向が強く見られます。
企業がどのような人材を求め、どのようなプロセスで採用するかは企業戦略や経営方針に深く関連しています。
そのため企業は自社のニーズを明確にし、それに合った採用プロセスを構築することが重要です。
日本企業が海外市場での競争力を高めるためには即戦力を求める選考プロセスを取り入れる必要があり、対して海外企業が日本市場に進出する際には長期的な育成を視野に入れた採用戦略が求められると言えるでしょう。
第2章 採用基準と評価方法の違い
採用プロセスにおける「採用基準」と「評価方法」は企業の文化や求める人材像を反映させる重要な要素です。しかし日本と海外の採用においてこれらの基準や方法にも大きな違いがあります。
本章では日本と海外の採用基準と評価方法の違いを掘り下げ、企業が採用戦略をどのように構築すべきかについて考察していきましょう!
<日本における採用基準と評価方法〉
日本企業における採用基準は主に次の2つの要素に分けられます。
❶人物重視の採用基準
日本の企業文化では採用基準として「人物重視」が非常に強調されます。
新卒採用では学歴や専門的なスキルよりも応募者が企業の価値観や文化にフィットするかどうかが重視されることが多いです。このため採用面接では応募者の「人間性」や「チームワーク力」、「誠実さ」などが評価される傾向があります。
適応力と成長性
日本の職場ではチームワークや調和が重要な価値として捉えられるため、応募者の協調性や周囲との調和性が高く評価されます。面接時にはグループディスカッションやロールプレイを通じて他者との関係性を観察する場面も多く見られます。
協調性と調和
日本企業は候補者の現時点でのスキルよりも企業文化に適応できるか、成長のポテンシャルを重視します。採用においては「将来の姿」が想定され、育成しながらスキルを上げていける人物を選ぼうとします。
❷ スキルよりも「育成の余地」重視
一般的に新卒者を一から育成する文化が根付いており、即戦力よりも将来性を重視します。そのため選考基準には「職務に必要なスキルが足りなくても、成長する可能性があるか?」という点が大きな判断材料となります。
研修制度やOJTの重視
多くの日本企業では採用後に研修制度やOJTを通じて、社員に必要なスキルや知識を身につけさせます。そのため面接時に求められるのはスキルや経験よりも、柔軟性と学ぶ姿勢です。
<海外における採用基準と評価方法〉
海外の企業では採用基準と評価方法は日本とは異なり、より即戦力を重視する傾向があります。主に2つの要素によって採用基準が設けられる傾向があります。
❶スキルと実績重視
海外企業では応募者が持っている具体的なスキルや過去の実績が採用基準として最も重視されます。特に中途採用の場合は応募者が過去にどれだけの成果を上げてきたかが評価の中心となります。
実績重視の面接
例えばアメリカの企業では過去の成果や実績に基づいた質問が多くなり、応募者が具体的にどのような状況でどのように業務を進めたか、どんな結果を得たかに焦点を当てます。面接では「成果を示せる証拠」や「数字で示せる業績」が強調されることが多いです。
特定スキルの証明
特にテクノロジー業界などではコーディングテストやポートフォリオの提出が求められ、実際に業務をこなすために必要なスキルを証明することが求められます。
❷ 応募者の適応力と文化的フィット感
海外でも「適応力」と「文化的フィット感」は重視されますが評価方法には違いがあります。日本と違って企業文化への適合性が選考過程で確認されることはありますが、応募者が即戦力であるかどうか、またその企業の目的や価値観に即して働けるかという点がより注力されます。
カルチャーフィットと実務能力
特にスタートアップやIT業界ではカルチャーフィットが重視されるものの、スキルや実務能力がそれに先立って評価されます。応募者の過去の実績や職務経歴書を基にその人が即戦力としてどのように貢献できるかが重要視されます。
以上、日本と海外では採用基準と評価方法において大きな違いがあることがお分かり頂けましたでしょうか?
日本企業は人物重視で特に新卒採用ではポテンシャルを見極め、育成することに重きを置いています。
一方で海外企業はスキルや実績を重視し、即戦力となる人材を求める傾向があります。
日本企業が海外で成功するためには即戦力を重視した採用プロセスを取り入れ、応募者のスキルや実績をより明確に評価する必要があるかもしれません。
そのためには採用プロセスを国ごとの特徴や市場動向に応じて柔軟に調整することが重要です。
Uターン・Iターン採用が注目される背景には主に地方における人材不足の深刻化と都市部での過密化があります。
少子高齢化が進む中で地方の労働人口は減少傾向にあり、多くの企業が優秀な人材を確保するのに苦戦しています。
一方で都市部では高い家賃や長時間通勤といった生活の負担が増え、地方での生活を見直す動きが広がっています。
またコロナ渦の際にテレワークやリモートワークが普及したことで、勤務地に縛られずに働く選択肢が広がったこともUターン・Iターン採用の追い風となっています。
これにより地方での働き方や生活が現実的な選択肢として多くの人に受け入れられるようになっています。
第3章 雇用形態と働き方の違い

企業の採用戦略や組織文化において「雇用形態」と「働き方」の選択は重要な要素となります。特に日本と海外の間でこれらの要素には顕著な違いが存在し、その違いが企業の人材採用やマネジメントに大きな影響を与えています。
本章では雇用形態や働き方に関する日本と海外の違いを具体的に分析し、それぞれの特徴や課題を深堀りします。
<日本における採用基準と評価方法〉
日本では伝統的な雇用形態や働き方が色濃く残っており、これらは企業文化や社会構造に強く根付いており、今もなお大きな影響を与えています。
❶終身雇用と年功序列
特に大手企業において「終身雇用」と「年功序列」の制度が長らく採用されてきました。これらの制度は労働者が一生涯にわたって同じ会社で働き続けることを前提とし、職務の昇進や給与は年齢や勤続年数によって決定されます。
❷フルタイム vs 非正規雇用
近年では正社員だけでなく、アルバイトや契約社員、派遣社員といった非正規雇用も増えてきています。特に非正規雇用者は安定した給与や福利厚生を享受できないことが多く、労働市場の不安定さが問題視されています。
❸働き方の変化とフレックスタイム制度
近年、日本でも働き方改革が進み、柔軟な働き方を提供する企業も増えてきています。特にフレックスタイム制度やテレワークの導入が進んでいますが、企業文化や規則により、フルフレックス勤務や在宅勤務が難しい場合も多く、依然としてオフィス中心の働き方が主流となっています。
<海外における採用基準と評価方法〉
海外では日本と異なり、柔軟な雇用形態や働き方が普及している国が多く見られます。特に欧米諸国では労働市場の流動性や個人主義の影響を受けて雇用形態や働き方が多様化しています。
❶労働市場の流動性と自由な転職
アメリカやヨーロッパでは転職が一般的であり、キャリアアップを目的に複数の企業で経験を積むことが奨励されます。雇用者と被雇用者の関係もよりフレキシブルで契約ベースであることが多いです。
❷フレックスタイム制度とリモートワーク
フレックスタイム制度やリモートワークが普及しており、働き方の柔軟性が確保されています。特にアメリカや欧州の企業では働く場所や時間を柔軟に設定できる環境が整備されています。
❸給与制度と福利厚生の違い
給与水準や福利厚生も多様化しており、個々の社員のニーズに応じてカスタマイズされたパッケージを提供する企業が増えています。
■成果主義とパフォーマンス評価
→特にアメリカの企業では給与や昇進がパフォーマンスに基づいて決定される成果主義が一般的です。社員の仕事の質や結果に基づいて報酬が決まるため個々の貢献度が重要視されます。
■福利厚生の多様性
→従業員の健康や福祉を支援するために柔軟な休暇制度や育児支援、社員向けのフィットネスプログラムなど福利厚生が多岐にわたります。またフレックス勤務やリモートワークを積極的に導入している企業もあります。
上記のように日本と海外では雇用形態や働き方において根本的な違いがわかりました。
日本の企業文化では終身雇用や年功序列が長い間重視されてきましたが最近では働き方改革により柔軟な働き方が求められるようになっています。
一方で海外では転職が一般的で成果主義や契約ベースの雇用が普及しています。またフレックスタイム制度やリモートワークの導入が進み、働き手に対して柔軟な環境が提供されています。
企業がグローバルな視点を持ち、多様な働き方に対応するためには日本の雇用制度や働き方を見直し、柔軟性を高めることが求められます。
第4章 採用活動における多様性とインクルージョン

グローバル化が進む現代社会において企業が競争力を維持し、持続可能な成長を実現するためには多様性とインクルージョンを採用活動において重視することが不可欠です。
日本と海外では多様性とインクルージョンへの取り組み方に違いがあり、採用活動においてもそのアプローチが大きく異なります。
本章では多様性とインクルージョンの概念を明確にし、日本と海外での採用活動における実践例を比較しながら企業がどのようにこれらを実現しているのかを具体的に考察します!
<日本における多様性とインクルージョンの採用活動〉
日本企業における多様性とインクルージョンへの取り組みは欧米諸国と比較するとまだ進んでいない部分も多いですが近年ではその重要性が認識され、積極的な取り組みが始まっています。
❶性別の多様性と女性活躍推進
日本では女性の社会進出が徐々に進んでいるものの、依然として管理職や経営層における女性の割合が低いという課題があります。このため女性活躍推進が採用活動において重要なテーマとなっています。
多くの企業が女性社員のキャリアアップを支援するためのプログラムを導入しており、ダイバーシティ推進室を設置して女性リーダーシップの育成や働きやすい環境作りを行っています。また企業は男女問わず平等に評価される採用基準を設け、特に技術職や営業職などで女性の採用を積極的に進めています。
❷障害者雇用の推進
日本企業でも障害者雇用の重要性が高まりつつあります。法律で義務付けられている障害者雇用率を達成するだけでなく、それ以上の数の障害者を積極的に雇用し、障害者の能力を活かせる職場環境の整備が進んでいます。
多くの企業が障害を持つ社員が働きやすいオフィス環境を提供し、テクノロジーを駆使して障害者の能力を最大限に活かす方法を模索しています。また採用段階でも障害者雇用を意識し、障害を持つ応募者へのサポート体制を整えている企業が増えています。
❸外国人社員の採用
グローバル化が進む中で日本企業も外国人社員の採用を積極的に行っています。日本語能力だけでなく、外国語能力や国際的なビジネス経験を持った人材を採用することで企業の国際競争力を高めています。
また日本の企業文化においては外国人社員が企業に溶け込むためのサポートが重要です。異文化理解を促進する研修プログラムや外国人社員のメンター制度を導入している企業もあります。
<海外における多様性とインクルージョンの採用活動〉
海外では多様性とインクルージョンに対する取り組みが非常に進んでおり、多くの企業がその重要性を認識しています。
❶性別平等とLGBTQ+の採用
アメリカや欧州では性別や性的指向に関わらず、誰もが平等に働ける環境を整えるために多くの企業が努力しています。例えばLGBTQ+フレンドリーな職場を作り上げるために性別に関する表現の多様性を認めるとともに性的指向や性自認に基づく差別を防ぐ取り組みを行っています。
また同性愛者やトランスジェンダーの採用を積極的に進める企業もあり、そういった取り組みは企業のブランド価値を高め、優秀な人材を引き寄せる要因ともなっています。
❷人種とエスニックバックグラウンドの多様性
アメリカやヨーロッパでは多様な人種やエスニックバックグラウンドを持つ人々が多く存在するため、人種間の平等を目指す取り組みが盛んです。企業は人種的な多様性を反映させるため、積極的に少数派の採用を進めています。
例えばブラック企業やヒスパニック企業向けに特化した採用プログラムや、アフリカ系アメリカ人やヒスパニック系の社員を対象にしたリーダーシップ研修が行われています。
❸障害者雇用とアクセシビリティ
海外企業でも障害者の雇用は重要なテーマです。特にアメリカでは、ADA(アメリカ障害者法)に基づき、企業は障害者に対する平等な機会を提供することが求められています。障害者向けのリモートワークの機会を提供する企業や障害者が快適に働けるオフィス環境を整備している企業が増加しています。
![]()
採用活動における多様性とインクルージョンは企業の成長において重要な要素であり、競争力を高めるためには欠かせない要素となっています。
日本と海外では多様性へのアプローチや実施方法に違いがあるものの、どちらの地域でもこれを推進するための取り組みが着実に進んでいます。
企業が積極的に多様性を受け入れ、インクルーシブな文化を育てることは将来的な成功を確保するために不可欠なステップとなるでしょう。
第5章 採用活動におけるテクノロジーの活用
近年、採用活動におけるテクノロジーの活用は急速に進んでおり、企業が効率的に優秀な人材を採用するための重要な手段となっています。人工知能(AI)、機械学習、データ解析、オンライン面接ツールなど様々な技術が採用活動に組み込まれ、採用プロセスの効率化や公平性の向上が図られています。
本章では採用活動におけるテクノロジーの最新の活用方法を日本と海外の事例を交えて具体的に説明し、その利点と課題を考察します。
<日本における採用活動のテクノロジー活用〉
日本の企業でもテクノロジーの活用は増えており、特にAIを使った採用システムやオンライン面接ツールが注目されています。ここではいくつかの具体的な事例を紹介します。
❶AI面接ツールの導入
日本の企業ではAI面接ツールを導入することで、面接プロセスを効率化しています。これにより、応募者はオンラインで事前に録画された質問に対して自分の回答を録音し、AIがその内容を解析して、候補者の適性を評価する仕組みです。AIは応募者の言葉遣いや表情、声のトーンを分析し、企業が求める人物像にマッチしているかを判断します。
こうしたツールを活用することで採用担当者はより多くの候補者を迅速に評価することができ、面接の公正性を保ちながら効率的に選考を進めることができます。さらに録画された面接内容は後から確認できるため、複数の面接官による評価やフィードバックも簡単に行えます。
❷オンライン採用イベントとウェビナー
新型コロナウイルスの影響でオンライン採用活動が急速に普及しました。特にオンライン採用イベントやウェビナーは企業が広範囲にわたる求職者にアクセスできる手段として注目されています。これにより地理的な制約を超えて、多くの候補者に企業の文化や採用情報を提供することが可能になりました。
例えば大手企業はオンラインプラットフォームを活用して、全国や世界各地から一度に求職者と交流する機会を提供しています。またウェビナーを通じて企業説明や質疑応答の時間を設け、候補者が企業に対する理解を深めることができる仕組みが整っています。
<海外における採用活動のテクノロジー活用〉
海外では採用活動におけるテクノロジーの活用がさらに進んでおり、特にアメリカや欧州では先進的なツールやプラットフォームが普及しています。
❶AIによるバイアス排除と公平性の確保
アメリカを中心に採用活動でのバイアス排除を目的としたAIツールが多く導入されています。AIは性別や人種に関わらず、候補者のスキルや経験に基づいて評価を行うため、採用プロセスの公平性を高めることができます。
例えばある企業ではAIによる履歴書スクリーニングツールを導入し、従来の人力によるフィルタリングで起こりやすかった性別や年齢による偏見を排除することができました。このような取り組みはダイバーシティとインクルージョンを推進する企業にとって大きな意味を持っています。
❷ビデオ面接とバーチャルリアル(VR)面接
海外企業ではビデオ面接が一般的な採用手法となっています。さらに最近ではバーチャルリアル(VR)面接が一部で導入されており、候補者が仮想空間で面接を行うことができるようになっています。これにより採用担当者と候補者が地理的に離れていても、リアルに近い面接体験を提供できるようになりました。
VR面接は特にリモートワークを行っている企業やグローバルに事業を展開している企業において採用の効率化と候補者の体験向上に貢献しています。
❸採用マーケティングとSNS活用
アメリカや欧州では採用活動におけるマーケティングとSNS活用が進んでおり、企業は求人情報をSNSプラットフォーム(LinkedInやFacebookなど)で積極的に発信しています。これにより潜在的な候補者との接点を増やし、優秀な人材を早期に確保することができています。
企業はSNSを活用して社員のインタビューや企業の文化を紹介することで、求職者に企業の魅力を直接伝えることができます。これは候補者が企業の文化にフィットするかどうかを、事前に確認できるとともに企業側も自社の魅力をアピールすることが可能です。
採用活動におけるテクノロジーの活用は企業の採用プロセスを効率化し、優秀な人材を迅速に獲得するための重要な手段です。
AIや機械学習を駆使したツールはスクリーニングから面接、最終選考に至るまで、さまざまな場面で活用されています。またオンライン面接やSNS活用なども求職者との接点を増やし、採用活動の効率を向上させる要因となっています。
日本と海外ではテクノロジーの活用方法に差があるものの、共通して言えることはテクノロジーの進化によって採用活動がより透明で効率的、かつ公正になっているという点です。今後、テクノロジーを活用した採用活動はさらに進化し、より多様な人材を取り入れるための新たな可能性を切り開いていくでしょう!
第6章 まとめ
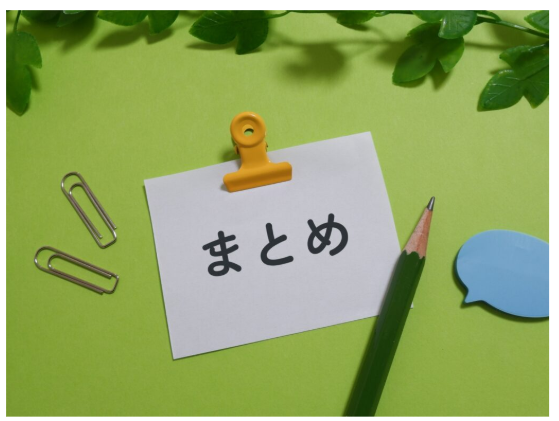
日本と海外の採用プロセスや評価基準には大きな違いがあることがお分かり頂けましたでしょうか。
日本では長期的な育成を前提とした採用が中心ですが海外では即戦力を求める傾向が強いのが特徴です。
グローバルな競争が激化する中で今後は日本企業も柔軟な採用戦略を取り入れることが求められるようになってくるでしょう。
しかし「海外の採用手法を取り入れたいが、何から始めればいいのかわからない」「自社の採用プロセスを見直したい」とお考えの企業も多いのではないでしょうか?

グローバル採用の知見をもとに即戦力人材の獲得や採用プロセスの効率化も支援しています。
貴社に合った採用手法を見つけたい方はぜひお気軽にご相談ください。
▶詳しいサービス内容や支援実績は弊社ホームページでご紹介しています。ぜひご覧ください!

また毎月発行している「採用戦略マガジン」では採用成功のための最新情報や具体的な施策を発信しています。
採用活動に関する様々なヒントを気軽に学べるマガジンとなっていますので
ぜひご活用ください♪
最新号だけではなく、過去のバックナンバーも”ダウンロードフォームにご希望月を入力”でGETできます!
■お問い合わせ先
株式会社採用戦略研究所
大阪府大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル 9F
TEL:06-4300-7120 MAIL:share@rs-lab.jp![]() 公式Facebook
公式Facebook ![]() 公式Twitter
公式Twitter